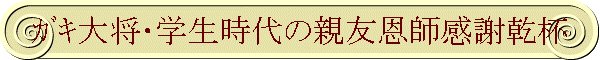
JH6NXC & Sakai Family’s HomePage 少年・学生時代の親友・恩師に感謝乾杯
18/01/16
修正
お気に入りの画像をクリック !!
最近、お風呂でゆっくりくつろいでいる時や、目が覚めてお布団の中にいるとき等によくアイデアが浮かんでくることが多い気がする。
小学校の低学年頃に、近くの年上のガキ大将と一緒に山に落とし籠でメジロとりに行ったり、田圃や畑にカスミ網でホウジロとりに行ったり、近くの竹山にチャンバラに行ったり、田圃に模型飛行機飛ばしに行ったり、正月の松の芯や柴とりに行ったり、枚挙に暇がない程で、遊びながらも社会集団生活等を学んできたと思っている。
そのガキ大将や家来の遊び仲間達に感謝し、出来れば乾杯をしたいと思う。ありがとう。乾杯。
又それ以降の学年でも、同じハレーボール部で頑張った仲間達、修学旅行で一緒に行動した仲間達、英会話のESSクラブの仲間達、これまた、枚挙に暇がない。そして、三角定規で頭コツン、罰当番、等など・・・・・。
大変お世話になった恩師の方々。高年になった現在、大変懐かしく思います。同窓会などでもお会い出来ない方も増えてきました。その方々も含めて感謝したい。ありがとう。乾杯。
○ガキ大将に感謝乾杯
幼稚園児の頃の記憶に残る遊びは殆ど思い出すことはない。
小学校に入ると直ぐに5,6年生の年上の先輩達との集団生活が始まる。当時は現在のような集団登校のなような記憶はなく、登校時間になると、ゾロゾロととあちこちから小学生が集まってきては、数人ずつ固まって遊びながら通学していた。
通学道路を大人のようにおとなしく歩いていることは少なく、道路に並行して続く道路より高い畦道に駆け上り走ったりしていたことが多かったように記憶している。ある時は、通学道路の側の田圃に「蛇」を見つけると、誰が言い出すでも無く、みんなで石を拾い集め、蛇に石を投げつけ殺してしまうこともあったし、通学道路をオート三輪車でも通るものなら、三輪車の荷台の後ろにぶら下がり走っていくことも有った。
小学校の運動会や夏休みなどの直前の注意事項や指導なども、部伍会と言われていたように思うものの定かでないが、上級生の6年生を中心に低学年をまとめた形の当時「部落」(今の部落とは違うが)と呼ばれていた集落単位にされていたように思う。
運動会の花形競技種目は、なんと言っても「部落対抗リレー」で子供達も大人達も総立ちになり大声援を送って1番でも上位の順位になるよう応援したものでした。運動会の前から、部落では1年生から6年生まで足の速い生徒を集め練習したものでした。この選手に選ばれることは子供にとっても親にとっても名誉な事でした。当方の長延部落では、当方と同学年の「近藤君」がピカイチの走りで、運動会では、大声援に答えて、何時も前の選手をゴボウ抜きにしてくれたものでした。
小学生になると、お宮掃除が待っており、部落単位の内、更に、神社単位に6年生を中心に小学生がグループ化されていた。
この当たりから、6年生のガキ大将が全員に命令しお宮の境内の掃除をさせると共に、掃除が終わると、「地獄のマラソン」が待っていた。
神社は集落より高台に有り、神社の脇を通る山道を山に向かって往復させる地獄のマラソンでした。今でも本当にきつかったことを覚えている。
6年生は5年生以下の時、6年生の先輩からこの地獄のマラソンを走らされており、自分達がやっと6年生になって先輩と同じように後輩を走らせているようだった。
当方が6年生になった時この地獄のマラソンはい廃止した。中学になったためその後の情報は全く知らない。
今考えると、子供時代の忍耐力増加のためには廃止しない方がよかったのかもしれない。
さて、これから、いよいよガキ大将が登場。
上述の部分はそれほどの回数は無いが、日常は遊びで始まって遊びで終わるのが普通である。
当方の場合は、自宅前の「テッコチャン」がお山の大将で当方がさしずめ家来と言ったところでしょうか。
殆ど、大将の家に入り浸りで遊ばせていただきました。
大将の家は進歩的な乳牛や梨やたばこなどと幅広く栽培されている農家で、いろんな道具がそろっていました。先ずは、大きく丈夫な縁台があり、漫画王などの漫画の本は置いてあるし、バレーボールや将棋やトランプ等や花札、百人一首等も有ったと思う。当時からトラクターやオート三輪車などもありました。昔は規制も無く、メジロも何羽も飼っててありました。農家の為家の前は広くドッヂボールで遊ぶのにはもってこいでした。
子供の頃、じっとしていることは少なく、日曜日などは良くテリトリーとしている野山にでかけたものです。
春先等は、近くの竹林に行き、鞍馬天狗のように風呂敷で覆面してチャンバラゴッコした記憶があります。竹を棒で叩くと「カンカン」と大きく響きわたるため、良く叩いたものでした。
大将の家は葉たばこの生産者だったため、家の広場には、落ち葉を集めてたばこの苗床ををいくつも作ってありました。ここに大将から「ジャックとまめの木」に出てくるようなマメの鞘が30cm前後にまで大きくなる「タッチャクマメ」なる種を貰って一緒に発芽させていただきました。牛の餌のサツマイモやトウモロコシやエン麦の刈り取り等にもついて行き手伝ったのか遊んだのかよくわかりませんが、良く遊ばさせてもらいました。
このような環境で遊びながら苗床で発芽させ家に持ち帰って大きく育てたり、イチジクの挿し木をしたり、我流で梅や柿の木を剪定したり、一緒に山取りした松の剪定をしたり、して遊びました。
正月近くになると、テリトリーとしている近くの山に分け入って、正月に必要な松の小枝や幸神柴やウラジロやユズリハや栗箸などを毎年一緒に取りに行ったものです。その合間には、赤松の林に行って、この赤松の根元付近に松茸が採れるなど現地で教えて貰いました。
時には、枝振りの良い黒松の苗木が有ると山取りして家に持ち帰ったものです。
ある時は、メジロ用の落とし籠を縁側の台で三ツメ錐や小刀を使い、鳥かご作りを一緒に始めたのは良かったが、竹を切るとき誤って指を怪我してしまいました。 かなり怪我は酷く、指の骨に達していたようで、今でもツメに傷の影響がでています。指先が切れて無くならず良かったなあとつめの傷を見るたびに思います。
家に何匹もメジロを飼ってありましたので、水浴びやサツマイモを良く噛んで唾液とよく混ぜた餌をあげること、鳥かご下に敷いてある糞の掃除用の新聞紙の取り替え等大変に手が係っていたようです。芋を噛んで餌を作ることはしたようですが、どんなことをして手伝ったか記憶しておりません。
そして、おとりのメジロを落とし籠の二段の下側に入れ、上の落とし籠に野生のメジロを誘い込み入った途端に蓋が閉まるようにした鳥かごを使用したり、鳥かごの近くの枝にトリモチを巻き付けて
これに止まって動けなくなったメジロを急いで捕まえる時などにも良く付いて行ったものです。
冬には大将はカスミ網を使ってホウジロ取りに行くので、その時もつれて行って貰いました。家来の当方は葉のついた竹でホオジロを藪から追い出すために走り回りました。又、家の裏の竹藪にカッチョを撮るための罠「ウッヅメ」の作り方も習いました。
夏には、大型の魚取りの網を持って小川や田圃の用水路の流れ込みの箇所を狙って足で追い込みフナなどを捕まえたり、「アクの木」の枝や根を上流側で叩きつぶし、その汁を流し「アク」で浮いたフナなどを捕まえることも手伝いながら覚えました。
秋の稲刈りが終わった田圃で、スポンジゴムのボールで野球を良く一緒にしました。少し田圃が湿っていると靴は泥だらけとなり、その状態で走り回るのでズボンの裾は泥だらけとなったものです。
当時、ゴムを動力とする模型飛行機作りが流行していて、「ささやま号」、「ライトプレーン」等ありましたが、「ささやま号」の性能がよりすぐれていたように思います。「ささやま号」は足が1本で滑走からスタートさせることはできませんでしたが、風向きに真上に向けての急上昇も可能で飛行時間も長く完成度の高い模型飛行機だったと記憶しています。
書き尽くす事は出来ませんが、優しいガキ大将「テッコチャン」から教わった事は多く、現在の家庭菜園、草花栽培、梅や松や柿や柑橘類の接ぎ木や剪定、バードウォッチング等々のベースになっているのは間違いありません。
本当に感謝感謝 !! そして乾杯 !! 乾杯!!
○学生時代の親友恩師に感謝乾杯
別のコンテンツ 「心の交流年賀状」に小学校、中学校の恩師を始め親友先輩の方々に対しての感謝について詳細に記載しておりますのでご参照ください。
本当に感謝感謝 !! そして乾杯 !! 乾杯!!
工事中